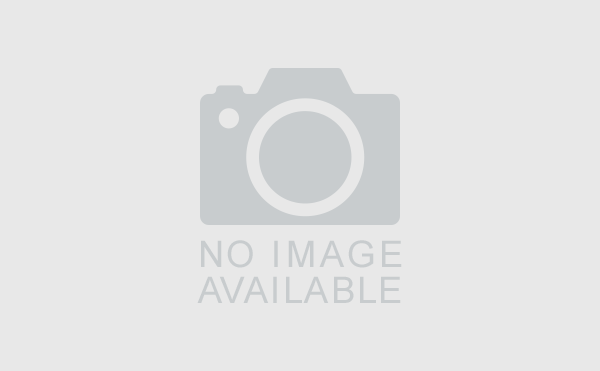贈与の成立時期とは?5つのパターンをやさしく解説
「そろそろ子や孫へ財産を渡していきたい」「生前贈与を活用したい」──そんなとき意外と盲点になるのが“贈与がいつ成立するか”というタイミングです。贈与税は「その年に成立した贈与額」で計算されるため、成立日を取り違えると課税時期や税額がずれてしまうことも。ここでは代表的な5つの贈与方法について、成立時期をやさしく整理します。
1.口頭での贈与──“渡した日”が成立日
「この時計、プレゼントするよ」と手渡した瞬間や、預金口座の名義を変更して使えるようにした日がゴール。契約書がなくても実際に財産が移った日で贈与が成立します。
2.書面による贈与(原則)──“契約書を交わした日”
贈与契約書を作成し、署名・押印を済ませた時点で成立。書面を残すことで、後のトラブル防止や税務調査への説明がスムーズになります。
3.書面による贈与(例外:不動産など)──“登記完了日”
土地や建物など登記が必要な財産は要注意。契約書があっても法務局で登記が完了した日まで贈与は成立しません。登記を後回しにすると、想定外の課税や権利関係のトラブルにつながることも。
4.停止条件付き贈与──“条件達成日”
「大学に合格したら1000万円を贈与する」といった条件付きの場合、条件が実現した日が成立日。条件が叶わなければ贈与自体が成立しません。
5.農地の贈与──“農業委員会の許可日”
農地は農地法の制限下にあり、贈与にも行政の許可が必須です。手続きには数か月かかることもあるため、農業委員会などの許可が下りた日を成立日としてスケジュールを立てましょう。
まとめ:タイミングを押さえて賢く資産承継
贈与の成立時期を正しく把握しておけば、贈与税や生前贈与加算(相続開始前3年以内の贈与が相続財産に戻されるルール)での想定外の課税を防げます。
特に不動産や農地など手続きが複雑な資産は、早めに専門家へ相談し「いつ・何を・どう渡すか」を一緒に設計するのがおすすめです。