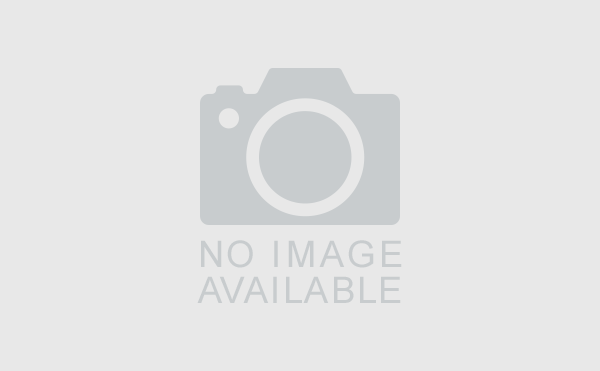不動産や株式などを売却(譲渡)して生じた利益は「譲渡所得」として課税されます。
しかし、譲渡所得が予想以上に大きくなると、住宅ローン控除や基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、そして寡婦・ひとり親控除なども所得制限により受けられなくなるリスクがあるのをご存知でしょうか?ここでは、譲渡所得の仕組みを簡単におさらいし、大きな譲渡益が発生した場合の注意点をわかりやすくまとめました。
1. 譲渡所得とは?
譲渡所得は、不動産や株式などの資産を売却したときに得られる利益を指します。
大まかな計算式は、次のとおりです。
譲渡所得 = 売却価額 -(取得費+譲渡費用)
- 取得費: 購入時の代金、仲介手数料、改修・リフォーム費用 など
- 譲渡費用: 売却時の仲介手数料、印紙税、測量費用 など
また、所有期間が5年以下なら「短期譲渡」、5年超なら「長期譲渡」となり、適用される税率が大きく変わります。
(売却日ではなく、その年の1月1日現在で5年を超えているかどうかを確認。)
(補足)株式の譲渡益は「源泉徴収あり特定口座」なら確定申告不要?
上場株式の売却益については、証券会社の「源泉徴収あり特定口座」を利用している場合、売却時に所得税・住民税が自動的に源泉徴収され、課税関係が完結します。
この場合、あえて確定申告をしなければ、株式譲渡益は確定申告書に記載されず、結果として合計所得金額にも含まれないため、住宅ローン控除などの「所得制限」には影響を与えません。
ただし、配当金や他の株式取引との損益通算や繰越損失の控除を受けるには申告が必要になるため、その際は譲渡益を申告書に記載し、合計所得に加算される点に注意してください。
2. 大きな譲渡益で控除が受けられなくなるかも
譲渡所得が想定以上に大きくなると、「合計所得金額」が膨らんで、
以下のような所得制限のある控除を使えなくなる恐れがあります。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
合計所得金額が一定額(例:2,000万円超)を上回ると利用不可。
譲渡所得は申告分離課税であっても合計所得の判定では合算されるため、売却益が大きいと制度の適用対象外になることがあります。 - 基礎控除
合計所得金額が2,400万円超~2,500万円超で段階的に縮減、2,500万円超で0円に。
譲渡益の急増により想定以上の合計所得金額となり、基礎控除を失うケースも。 - 配偶者控除・配偶者特別控除
納税者本人の合計所得金額が一定水準(例:1,000万円超〜1,220万円超など)を超えると、配偶者を扶養していても適用が制限される可能性があります。
譲渡益が大幅に出たことで合計所得が急上昇し、控除を失う事例があるため注意してください。 - 寡婦控除・ひとり親控除
所得制限の要件として合計所得金額が500万円以下など、一定の基準を設けている場合があります。
譲渡益が大きいとその基準を超えてしまい、結果として寡婦・ひとり親控除が適用できなくなることがあります。
このように、譲渡益が増えるほど合計所得金額が上昇し、いろいろな控除の適用要件を満たせなくなる“連鎖的なリスク”がある点を覚えておきましょう。
3. 居住用不動産の優遇や特例にも要注目
マイホームとして使用していた不動産を売却する場合、3,000万円特別控除や軽減税率などの特例を受けられるケースがあります。
ただし、店舗併用住宅などは居住部分の面積区分が必要だったり、ほかの特例と重複できるか否かは条文ごとに異なったりするため、必ず事前に条件を確認してください。
4. 押さえておきたいポイント
- 取得費・譲渡費用を正確に計上
購入時・売却時の仲介手数料や契約書、リフォーム領収書などを紛失すると、譲渡所得が不必要に大きく計算され、合計所得金額がさらに上昇する恐れがあります。 - 短期・長期の境目は1月1日
わずかな日数差で税率が変わることがあるほか、合計所得金額にも影響が出るため、売却タイミングの見極めが非常に重要です。 - 大きな売却益が出そうなら事前に試算
住宅ローン控除・配偶者控除・寡婦控除などを残したい場合、売却時期を年をまたぐ形で調整できないか検討するなど、事前のシミュレーションが欠かせません。 - 専門家へ早めに相談
税制改正や個別事情(複数物件・併用住宅・買換え特例など)により扱いが変わることが多いので、専門家に相談して最適なシミュレーションを行うのがおすすめです。
5. まとめ
譲渡所得が増えると、その分合計所得金額が想定以上に上がり、住宅ローン控除、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、さらには寡婦・ひとり親控除まで受けられなくなるケースがあり得ます。
思わぬ税負担増を防ぐためには、取得費の精査や売却タイミングの調整、各種特例・控除の正しい組み合わせを考えることが大切です。
当事務所では、譲渡所得に関するシミュレーションや特例の適用可否、控除の維持方法などをサポートしております。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ お問い合わせ ▼