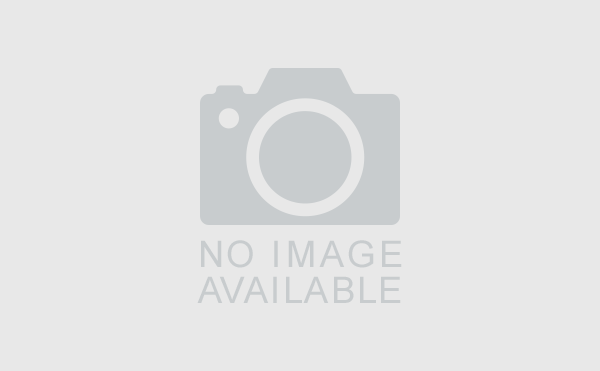法人化すべきか?個人事業のままか?
「売上が増えてきたけど、そろそろ法人にした方がいいのかな?」
個人事業主として数年活動していると、こんな疑問を持つ方が少なくありません。事業が軌道に乗ってくるにつれ、節税や信頼性の面で「法人化」を検討するタイミングがやってきます。
ただし、法人化にはメリットと同時に、負担やコストの増加というデメリットも存在しますので、法人化の判断基準について解説します。
法人化のメリット
1. 節税効果が期待できる
個人事業は所得が高くなるほど税率も上がる「超過累進課税」が適用されます。一方、法人税は基本的には一定水準の税率(中小法人向けの軽減税率など若干の変動はあり)です。所得が大きくなってくると、個人事業よりも税率の面で有利になることがあります。
さらに、法人にすると自分の給与を「役員報酬」という形で支払うことができ、その範囲で所得を分散できます。家族を役員にして報酬を支払えば、家族の所得として計上し、家族全体で税負担を抑えられるケースもあります。ただし、役員報酬は「役員会議の議事録」「報酬の合理性」など、一定のルールや手続きがある点に注意が必要です。
2. 経費の範囲が広がる
法人では、社宅制度や出張旅費規程などを整備することで、個人事業よりも柔軟に経費を計上できる可能性があります。結果的に手元に残るお金(実質的な手取り)が増えることがあります。ただし、これらの制度を適切に運用するためには、社内規程の整備や税理士への相談などが必要です。
3. 社会的信用が高まる
法人になることで、取引先や金融機関からの信頼性が高まります。事業拡大を目指す場合や融資を受けたい場合は、法人形態の方が有利に働くことが多いです。最近はフリーランスや個人事業主でも活躍しやすい時代ですが、それでも「法人」という形態が重視される場面は依然として少なくありません。
法人化のデメリット
1. 設立・維持コストがかかる
法人設立時には「登録免許税」や「定款認証費用」などが発生し、設立後も毎年最低でも法人住民税(均等割)がかかります(7万円程度〜)。また、会計や税務処理が複雑になるため、専門家に依頼するケースが増え、その分の費用も必要となります。
2. 事務負担が増える
法人の場合、決算書の作成や株主総会(家族経営でも形式上は必要)、社会保険の加入・届出など、事務手続きが格段に増えます。小規模な事業であっても、これらの作業に時間と手間をとられるため、本業に支障が出るリスクもあります。
3. 社会保険料の増加
個人事業主の場合は、国民健康保険や国民年金への加入が主流ですが、法人化すると、役員や従業員として健康保険・厚生年金への加入義務が発生します。保険料の自己負担(法人負担と本人負担の両方)が増える場合が多いので、実質的な手取りが減少する可能性もあるでしょう。2025年以降は、社会保険料率の引き上げが議論されており、コスト増につながる可能性も考慮しておきましょう。
法人化の判断基準
1. 年間所得の目安
課税所得が700万〜800万円を超えるあたりから、法人化によって「手取りベース」でメリットが出やすくなるケースが多くなります。ただし、扶養家族の有無や社会保険の加入状況、事業の経費割合などによって結果は大きく変わります。
そのため、法人化を検討する際は、単純に節税額を見るだけでなく、社会保険料や事務負担も含めたトータルでのシミュレーションを行うことが重要です。将来的な事業の拡大やライフプランも踏まえて、慎重に判断しましょう。
2. 家族に給与(役員報酬)を支払いたい場合
法人化すれば、専従者給与よりも柔軟な形で報酬設定が可能です。計画的に所得分散を行いたい方に向いています。
3. 今後の事業拡大や融資を考えている場合
法人であることが信用力に直結する場面は多くあります。とくにインボイス制度が定着しつつある今、法人である方が取引先から好まれるケースも増えています。
まとめ:安易な法人化は避け、プロに相談を
「節税になるから」「信用力が上がるから」といった理由だけで法人化するのはおすすめできません。法人化には多くのメリットがある一方で、設立コストや社会保険料などの負担も大きくなります。特に2025年以降は、社会保険や税制関連の変更によって、個々の事業者の状況がさらに多様化する可能性があります。ご自身のライフプラン・事業計画・収支状況を踏まえて総合的に判断することが重要です。不安や疑問を感じたら、専門家に相談しながらシミュレーションしてみましょう。